うさぎは愛らしい反面、非常にデリケートな生き物です。
「昨日まで元気だったのに…」が本当に起こる動物でもあります。
見た目では元気そうでも、実は体の中で病気が進行していることも。
この記事では、初めてうさぎを飼う方に向けて、うさぎがかかりやすい代表的な病気をわかりやすく紹介し、その原因・症状・予防法・実例も交えてまとめました。

【1】うっ滞(胃腸うっ滞・毛球症)
どんな病気?
うさぎの胃や腸の動きが鈍くなり、食べ物や毛が停滞することで消化が止まる状態です。人間で言えば“激しい便秘+胃もたれ”のようなイメージです。
原因と背景:
・ストレス(温度差・環境の変化・引っ越しなど)
・水分不足・運動不足
・換毛期に飲み込んだ毛が胃に溜まる
・繊維(牧草)不足で腸の動きが止まる
なりやすいタイプ:
・神経質・怖がりな子
・換毛期にあまりブラッシングされない子
・ペレット中心で牧草をあまり食べない子
初期症状:
・ごはんを食べない、水を飲まない
・うずくまって動かない
・ウンチが極端に少ない・出ない
予防法:
・毎日牧草をたっぷり与える(チモシー中心)
・新鮮な水をいつでも飲めるように
・換毛期は毎日ブラッシング
・へやんぽで運動時間を確保する
こはくの実例:
こはくは過去にうっ滞と腸閉塞を経験しました。… すぐに夜間病院へ連れて行き、点滴と薬を処方してもらい、その日のうちに回復。うさぎが食べない=命の危険なので、即病院が大事だと実感しました。

【2】不正咬合(ふせいこうごう)

どんな病気?
うさぎの歯は一生伸び続けます。特に奥歯(臼歯)のかみ合わせがズレると、歯が口内に突き刺さったり、目や鼻に影響を与えたりします。
原因と背景:
・牧草不足による咀嚼回数の低下
・先天的な歯並びの問題
・顎のズレや骨格の異常
なりやすいタイプ:
・柔らかい食べ物中心の食事
・歯を削るおもちゃや繊維質が足りない子
初期症状:
・ごはんをポロポロこぼす
・よだれが増える、顎が濡れる
・涙が出る、目が腫れる(奥歯の根が目を圧迫)
予防法:
・牧草中心の食生活を徹底する
・「歯が削れるか」を基準に食事を見直す
・半年~1年に一度、病院で歯のチェック
こはくの場合:
今のところ不正咬合はないですが、涙が続くようなら奥歯の根元が原因の可能性もあるので、定期的なチェックを受けるようにしています。
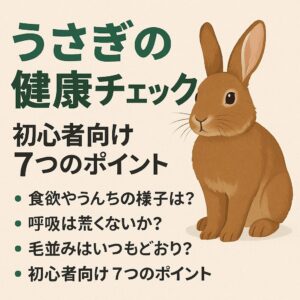
【3】スナッフル(うさぎの風邪・呼吸器疾患)

どんな病気?
人間の風邪のような症状ですが、原因はパスツレラ菌などの細菌感染が主です。
慢性化すると呼吸器が常に炎症を起こし、一生治らない持病になることも。
原因と背景:
・寒暖差(エアコン直風、急な冷え)
・免疫力の低下、ストレス
・ケージ内のホコリ・アンモニア臭
なりやすいタイプ:
・換毛期や体調を崩した直後の子
・引っ越しや通院後など、ストレス下の子
初期症状:
・くしゃみ、鼻水(透明→白濁)
・鼻の周りが濡れている
・呼吸時にピーピーと音がする
予防法:
・室温は年中20〜25℃をキープ
・加湿器で湿度も保つ(40〜60%)
・掃除と換気をこまめに行う
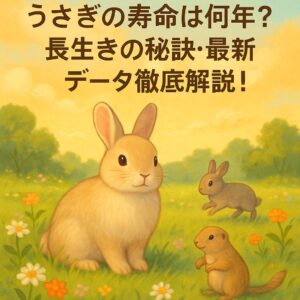
【4】皮膚炎・ツメダニ・かゆみの病気

どんな病気?
皮膚に炎症が起きたり、外部寄生虫(ツメダニやノミ)によってかゆみ・脱毛・フケが出る症状です。
特にツメダニは目に見えにくいため、発見が遅れやすいです。
原因と背景:
・湿度が高く、ケージ内が蒸れる
・不衛生なトイレ・寝床
・他の動物からの感染(ペットショップや多頭飼育)
なりやすいタイプ:
・換毛期のタイミングでブラッシング不足な子
・高齢・免疫力が落ちている子
初期症状:
・背中に白いフケが出る
・耳や首元をかく行動が増える
・皮膚が赤くなったり、かさぶたができる
予防法:
・ケージは週1で水洗い&完全乾燥
・換毛期は1日1回ブラッシング
・寝床やマットも定期的に取り替える

【5】斜頸(しゃけい)・エンセファリトゾーン感染症

どんな病気?
うさぎの首が傾いたまま戻らなくなったり、ぐるぐると旋回してしまう神経系の異常 原因のひとつがエンセファリトゾーン(E. cuniculi)という寄生性原虫です。
原因と背景:
・感染ルートは母子感染や排尿による接触感染
・ストレスや免疫低下がきっかけで発症することも
なりやすいタイプ:
・保護うさぎや繁殖背景不明な子
・免疫が落ちているタイミング
初期症状:
・首が左右どちらかに傾く(軽度)
・ぐるぐる回る(重度)
・目が揺れる(眼振)
予防法:
・ストレスを減らす(急な環境変化を避ける)
・体調が怪しいときはすぐ通院
・保険加入や夜間対応病院の確認も事前に
ひすいの実例:
ひすいをお迎えしたとき、目に白い模様がありました。
病院で診てもらうと「エンセファリトゾーンの疑い」とのことで、1週間ほど内服薬を続けました。
幸い、進行せず回復してくれましたが、初期対応の速さがカギだと痛感しました。

【6】尿石症・膀胱炎

どんな病気?
尿にカルシウムなどの成分が沈殿し、結晶や石となって排尿障害を引き起こす病気です。
ひどいと膀胱や尿道が傷つき、血尿や激しい痛みにつながります。
原因と背景:
・水分摂取量が少ない
・カルシウム過多のペレットや野菜を継続的に与えている
・肥満や運動不足で代謝が落ちている
なりやすいタイプ:
・水を飲む量が少ない子(ボトルより皿の方が飲みやすい場合あり)
・シニア期に入った子
・よく寝そべってばかりで動かない子
初期症状:
・白く濁った尿が出る(カルシウム)
・血尿、トイレで力む
・排尿時に鳴く、嫌がる
予防法:
・水皿+野菜で水分量を増やす
・カルシウムの多い野菜(チンゲン菜など)を控える
・へやんぽで毎日20〜30分は動かす


【7】肥満・運動不足

どんな病気?
肥満は単なる“見た目”の問題ではありません。うっ滞、関節痛、尿石症、皮膚炎など多くの病気のリスクを高める原因になります。
原因と背景:
・おやつやペレットの与えすぎ
・へやんぽの時間が足りない
・シニア期に入り代謝が落ちている
なりやすいタイプ:
・おやつに反応してすぐ食べてしまう子
・ケージ内で過ごす時間が長い子
初期症状:
・おしりが汚れやすい、足の裏が赤くなる
・走らない、ジャンプしない
・抱っこすると以前よりずっしり重く感じる
予防法:
・食事量は計量してコントロール(ペレットは体重×1〜1.5%が目安)
・へやんぽは毎日20〜30分以上
・体重は月1で測って記録しておく


【8】熱中症・ショック・突然死
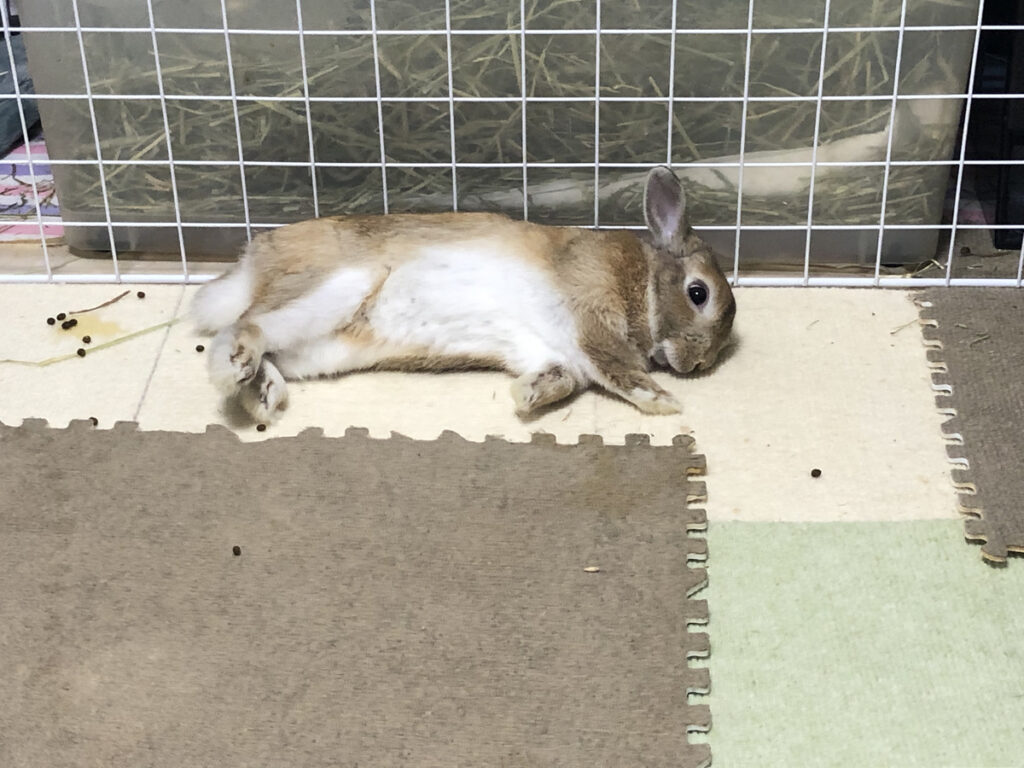
どんな病気?
うさぎは暑さにも寒さにも弱い動物です。特に夏場は28℃以上で熱中症になる危険性があり、命にかかわる急変もあります。
原因と背景:
・室温が高すぎる(直射日光・風通しの悪さ)
・高湿度+多頭飼育などの蒸れ環境
・うっ滞やストレスからのショック状態
なりやすいタイミング:
・夏の昼間の室温管理が甘い時
・換毛期・発情期など体力を使う時期
初期症状:
・呼吸が早くなる、ぐったりして動かない
・耳が異常に熱い or 冷たい
・目に力がなく、反応が鈍い
予防法:
・エアコン+サーキュレーターで常に空気を回す
・温湿度計を設置して常にチェック
・冷感マットやペットボトル氷も活用

【9】目の病気(流涙症・鼻涙管閉塞・白濁など)

どんな病気?
うさぎの目の病気は目そのものだけでなく、歯や鼻涙管(びるいかん)の異常から起きることが多いです。
原因と背景:
・不正咬合による歯根の圧迫
・鼻涙管の詰まり(炎症・感染)
・エンセファリトゾーンや外傷による白濁
・アレルギー、異物混入、換毛期の刺激
なりやすいタイミング:
・歯が伸びすぎている時
・換毛期で目の周りに毛が多い時
・乾燥した季節
初期症状:
・涙が止まらない(片目 or 両目)
・目の周りが赤くただれる
・白い膜や濁りが見える
予防法:
・歯のチェックは定期的に(半年〜1年ごと)
・ケージ内のホコリや牧草の粉に注意
・換毛期は目の周りも優しくブラッシング
こはくの実例:
こはくは涙が止まらない時期がありました。
見た目では元気でも「目がずっと濡れている」状態が続き、心配になって病院へ。
獣医さんの話では奥歯の根っこが目の周辺に影響を与えているケースも多いとのこと。
結膜炎や鼻涙管閉塞だけでなく、全身のチェックが必要だと実感しました。

🐾 おわりに|“気づく力”が命を守る
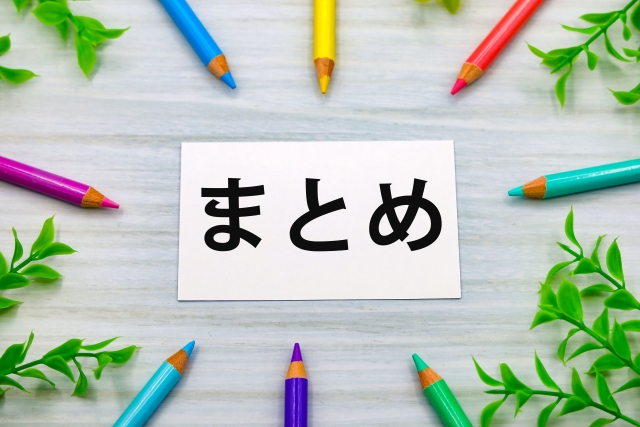
うさぎは不調を隠す生き物です。
だからこそ、「いつもと違うな」と気づいてあげられるかが本当に大切です。
食べない、うずくまる、涙が出ている、動かない、音に鈍感…
どんな小さな変化も見逃さず、早めに行動することで救える命があります。
我が家の「こはく」も「ひすい」も、早期発見と通院で命を守ることができました。
この記事が、あなたとうさぎさんの毎日を守るヒントになればうれしいです。



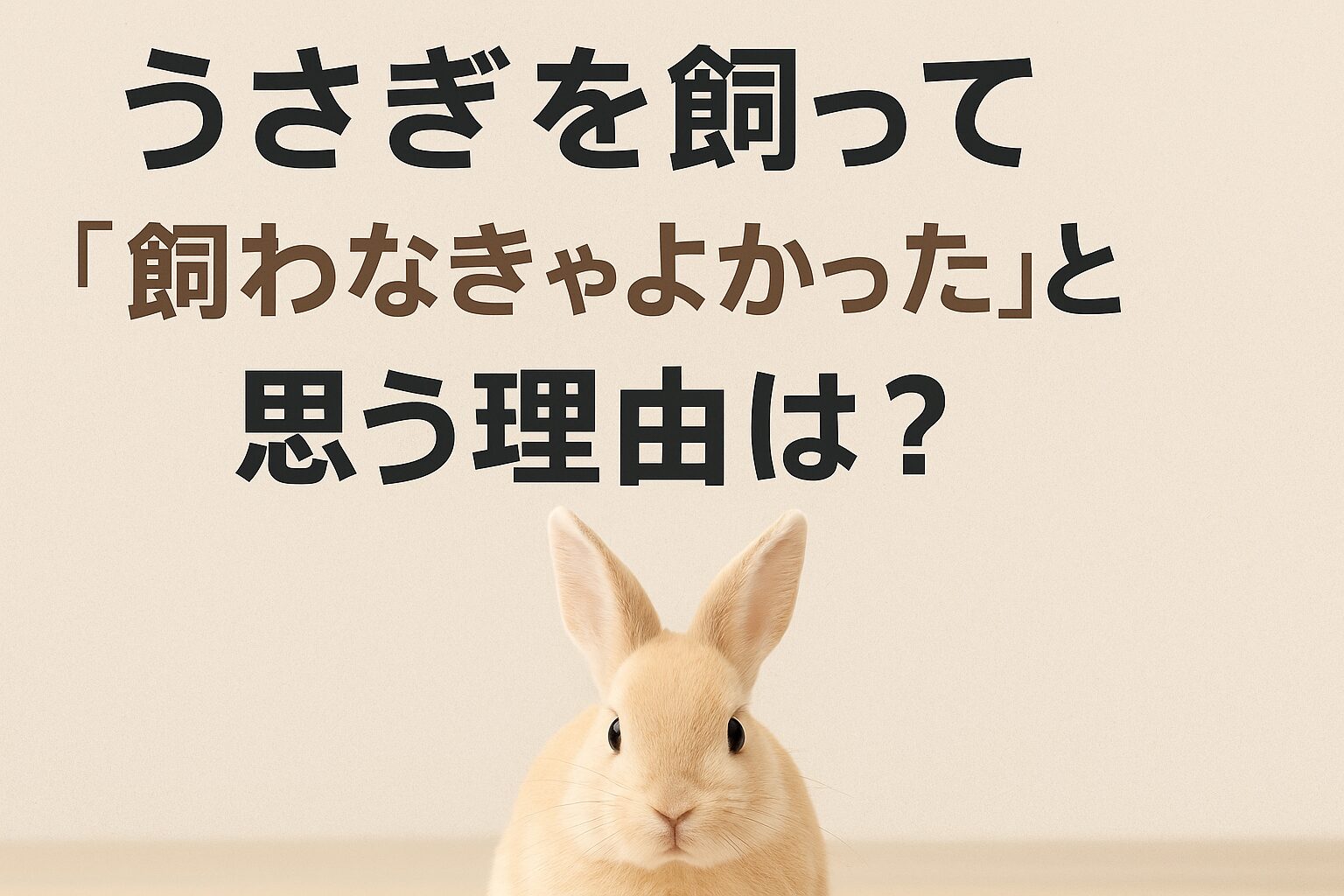

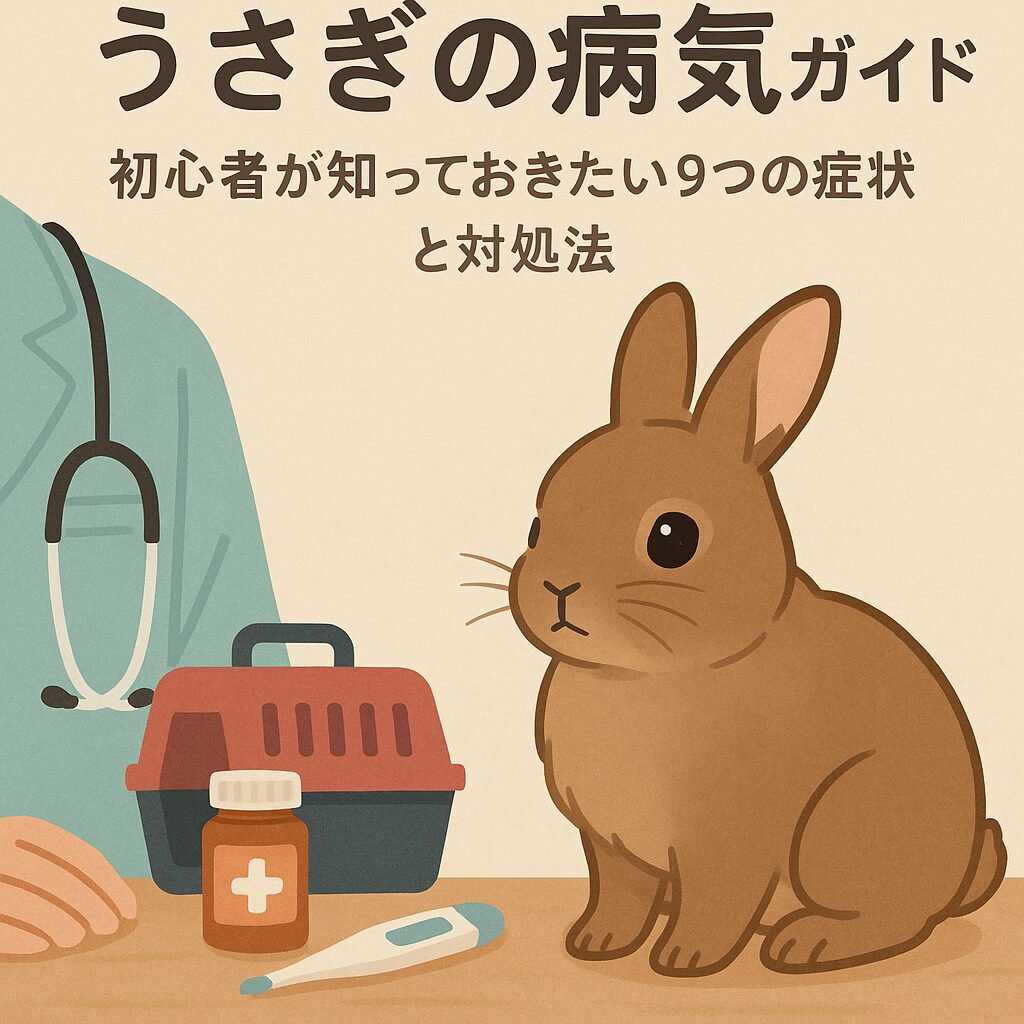
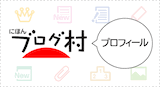









コメント