「リチャードソンジリスってなに?可愛いけど飼えるの?」「どんな性格?ちゃんとなつくの?」──そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事ではリチャードソンジリス歴2年の私が、リアルな経験をもとにその魅力と飼育のコツを徹底解説します。
お迎え前に知っておきたいポイントから、性格・飼い方・病気の予防法・価格相場まで、初心者の方も上級者の方も役立つような内容を1章ずつ丁寧にまとめました。
うちの子「ライ」(オス・2歳)との実際のエピソードもたくさん交えていますので、「飼ったあとのリアル」が気になる方にもきっと参考になるはずです。
どうぞ最後までじっくりご覧ください🐿️
リチャードソンジリスの基本知識
リチャードソンジリスとは?個体の特性と生態の紹介
リチャードソンジリスは、北アメリカ原産の地上性リス(ジリス)の一種で、草原や開けた土地に巣穴を掘って生活しています。同じリス科に属するプレーリードッグと見た目が似ていることから混同されやすいのですが、分類上は異なる属に属する別種の動物です。
うちの子「ライ」も、自分の気分をハッキリ表現するタイプで、嬉しいとぴょんぴょん跳ねたり、「キュッ」と鳴いて甘えてくる一方、構ってほしくないときはスルー(笑)。このツンデレさもたまりません。

リチャードソンジリスと他の小動物の違い
リチャードソンジリスは、「ハムスターやチンチラと何が違うの?」とよく聞かれることがあります。見た目は小動物っぽいのに、飼ってみるとまるで“小さな犬”のような存在感があるのが特徴です。
まず、昼行性である点は大きな違いです。ハムスターは夜行性なので、昼間は寝ていて触れ合いにくいこともありますが、リチャは日中に活発に動き回るため、飼い主の生活リズムと合いやすいんです。
また、感情表現の豊かさも大きな魅力。うちのライは機嫌がいいときはぴょんぴょん跳ねて寄ってきたり、甘えるような声を出してアピールしてくれます。逆にイライラしているときは「プププ…」と鼻を鳴らしたり、ケージの奥に引きこもったり(笑)。この“ツンデレっぽさ”がまた可愛いんですよね。
チンチラやデグーも賢くて魅力的な小動物ですが、リチャは人間に対する興味が強く、信頼関係が築きやすい印象があります。もちろん個体差はありますが、毎日話しかけたり、手からおやつをあげたりと、コミュニケーションを重ねていくことで徐々になついてくれるのが嬉しいポイントです。

リチャードソンジリスの野生環境と飼育環境の違い
野生のリチャードソンジリスは北米の広大な草原地帯に生息しており、仲間と一緒に地下トンネルを掘って生活しています。一方、私たちが室内で飼育する環境では、その本能的な習性をできるだけ満たす工夫が大切になります。
ライもよく床材の中に潜って巣作りのような動きを見せたり、タオルの下に隠れたりと、“掘る・隠れる”行動が見られます。なので、ケージ内にはトンネル状のおもちゃやかくれんぼスペースを必ず用意しています。

リチャードソンジリスの飼い方

初めての飼い主向け!リチャードソンジリスの飼育の基本
リチャードソンジリスの飼育は、初心者でもしっかり準備すれば十分可能です。ただし、単に「小さくて可愛いから」といった理由だけで飼うと後悔してしまうケースもあります。
我が家のライもお迎えした当初は、環境の変化に戸惑い、しばらくは警戒して近づいてきませんでした。人間に慣れるには時間がかかりますし、毎日の観察と信頼関係が必要です。

必要なケージの選び方とレイアウト
我が家のライは、ガラス製のケージで暮らしています。アクリルよりも重量がありますが、断熱性が高く、冬でも室温が安定しやすい点がお気に入りです。においがこもりにくく、掃除のしやすさもメリットです。
そしてベッドはなんと、人間用のフットクッション(足を中に入れるタイプ)を再利用!ライはこのクッションの奥に頭を突っ込んで、気持ちよさそうに寝ています。中がふわふわで、巣穴のような安心感があるようです。
ケージ内には回し車も設置しています。リチャは運動が大好きで、ライも夜になると楽しそうに走っています。足腰の健康維持やストレス発散にも効果的です。

食事と栄養バランス:ペレット・チモシーの重要性
ライはチモシーが大好きで、特に一番刈りのシャキシャキしたものをよく食べます。気分によっては柔らかめの三番刈りしか食べないこともあり、食べ比べて好みを探すのも楽しいですよ。

トイレトレーニングと環境作りのコツ
リチャードソンジリスはトイレの場所を完璧に覚えるのは難しいですが、ある程度「決まった場所にする」傾向があります。
最初はペットシーツも使っていましたが、ライは砂を好むタイプだったので現在のスタイルに落ち着きました。おしっこの色や量がわかりやすいのも、健康管理に役立っています。
ただし、発情期やストレスがあると突然別の場所で排泄することもあるため、温度・湿度・音・光など、快適な環境づくりも大切なポイントです。

リチャードソンジリスの性格とコミュニケーション

リチャードソンジリスの性格を理解する
我が家のライはまさにそんな性格で、機嫌がいいときは近寄って手をペロペロ舐めてくれるのに、気分が乗らないときは完全スルー…。でもそのツンデレ感がまた愛おしいんです。
もちろん、性格は個体差があるので、「すぐ懐く子」もいれば「数ヶ月かけてようやく慣れてくる子」もいます。

なつくための接し方と遊び方
「どうすれば懐いてくれるの?」という疑問は、私自身も最初に悩んだポイントです。結論から言えば、“焦らないこと”が一番大切です。
ライとの信頼関係も、最初の1ヶ月はほとんど進展がなく、「この子、私のこと嫌いなのかな?」と思ったこともありました。でも、毎日同じ時間に声をかけたり、エサを手からあげたり、小さな積み重ねを大事にしたことで、少しずつ距離が縮まっていきました。
今では名前を呼ぶとこちらを見たり、砂浴びしている最中に軽く触っても怒らなかったりと、だいぶ心を許してくれています。
一緒に遊ぶ際は、無理に抱っこしたり追いかけたりせず、まずは近くで見守るところから始めるのがおすすめです。

リチャードソンジリスの健康管理
一般的な病気とその対策
リチャードソンジリスは一見元気そうに見えても、実はとても繊細な生き物です。特に注意が必要なのが、歯の不正咬合(オドントーマ)です。
手術を経て、現在は元気に過ごしていますが、「異変に早く気づくこと」の大切さを実感しました。

寿命を延ばすための健康チェック
リチャードソンジリスの平均寿命は5〜7年ほどと言われていますが、適切な環境とケアによってさらに長く一緒に暮らすことも可能です。
また、定期的に「体重」を測るのも重要な習慣です。ライは成長と共に少しずつ体重が増え、現在は約340g。増減が大きいときは食事量や体調をすぐ見直します。

リチャードソンジリスの値段と販売情報

リチャードソンジリスの価格帯と相場
我が家のライをお迎えしたのは春頃で、価格は59,800円でした。お店には10匹以上のリチャが並んでいましたが、ライはくりっとした目でこちらをじっと見つめてきて…その瞬間に「この子だ」と決めました。
流通量が増える春〜初夏は選べる個体も多く、お迎えのチャンスですが、人気が高まっていることもあり、以前より価格が高めになってきている印象です。特に健康状態が良く、性格のおだやかな子はすぐに決まってしまうことも多いため、タイミングも大事です。

信頼できる販売店舗の選び方
お迎えするうえで最も重要なのが、「信頼できる店舗・ブリーダーかどうか」。健康状態や親の情報、飼育方法について丁寧に説明してくれるかが判断のポイントです。
ライを購入したお店では、性別や生年月日はもちろん、「この子は食が細めなので、ペレットより先にチモシーを多めに」といった個体の性格や特徴まで教えてくれました。こういった説明があるお店は信頼できる証拠です。
また、可能であれば何度か足を運び、スタッフの対応や清潔感なども確認しましょう。即決せず、慎重に選ぶことが大切です。
譲ります・販売する際の注意点
やむを得ず手放す場合や、繁殖により「譲ります」となるケースもありますが、これは簡単にできるものではありません。繁殖は難易度が高く、特にオスとメスを見分けるのも容易ではないため、軽い気持ちで考えるのはNGです。
万が一譲渡を検討する場合は、相手の飼育環境をきちんと確認し、動物愛護の観点からもしっかりした手順で行うことが大切です。
リチャードソンジリスの繁殖と冬眠

繁殖の基本知識と注意点
リチャードソンジリスの繁殖は非常にデリケートで、初心者には難易度が高いと言われています。繁殖期は春~初夏に集中し、メスは1度の出産で5〜10匹前後を産むこともあります。
繁殖に興味のある方や、すでに複数飼いをされている方は、以下の記事を必ずチェックしておくことをおすすめします。

冬眠について:リチャードソンジリスの休眠期間
リチャードソンジリスは、野生では冬になると地下の巣穴にこもり、「休眠状態(いわゆる冬眠)」に入ります。ただし、飼育下で冬眠させるのは非常に危険です。
実際に、急激な冷え込みで体温が低下し、「動かない」「反応が鈍い」といった症状が出て、そのまま亡くなってしまった例も報告されています。
ライも11月〜2月頃は活動量が少し落ち、昼間に寝ている時間が長くなりますが、それはあくまで“疑似的な季節反応”の範囲。ケージ内の温度は20〜25℃をキープし、急激な冷えを避けるよう心がけています。
冬季は特に、保温マットやパネルヒーターを活用して体温低下を防ぐ環境作りが重要です。「あれ?今日は動かないな」と思ったら、すぐに体温・呼吸・目の様子を確認してあげてください。
リチャードソンジリスを迎える前に知っておきたいこと
後悔しないための準備と心構え
リチャードソンジリスをお迎えする前には、「可愛い」だけでは済まされない現実もきちんと知っておくことが大切です。
私もライを迎える前は、InstagramやYouTubeで見る「可愛い姿」ばかりに惹かれていたのですが、実際に暮らし始めるとトイレの場所に困ったり、においが気になったりと、思わぬ苦労もたくさんありました。
特に大切なのは、「鳴き声が大きい」「発情期に攻撃的になることがある」「なつくのに時間がかかる」といった“リアルな一面”を知っておくこと。どんな動物も完璧ではないからこそ、事前の理解がとても重要です。
飼育にかかる初期費用や、必要なアイテムも想像以上に多くなりがちなので、できる限り前もって情報を集めておきましょう。

個体を選ぶポイントと体重の見方
ショップでリチャードソンジリスを選ぶとき、「この子だ!」と直感で選ぶのも良いですが、健康状態や性格の傾向をよく観察することが大切です。
ライを迎えたときは、店員さんが「この子はおっとりしていて、少し食が細めかも」と教えてくれました。その通り、最初の頃はチモシーをちょっとずつしか食べず、体重もなかなか増えませんでした。
個体の体重は成長具合や健康の目安になります。お迎え時に250〜300g前後の子が多いですが、急激な増減がないかを見てあげるのも大切なチェックポイントです。
ペット保険への加入も検討しておくと、いざというとき安心です。私も一度「加入しておけばよかった」と思う場面がありました…。

よくある質問(FAQ)
リチャードソンジリスの性格に関する質問
- なつきますか?
-
個体差はありますが、しっかり時間をかけて接すればなついてくれる子が多いです。
我が家のライも最初は警戒心が強かったですが、半年ほどかけてようやく手からエサを食べたり、近くで寝るようになりました。焦らず、根気よく関係を築くことが大切です。あわせて読みたい リチャードソンジリスは懐く?性格・個体差・懐かせるコツまで解説 小さくて愛らしい姿が人気のリチャードソンジリス。SNSやYouTubeなどでもその可愛らしい仕草が注目を集めていますが、「本当に懐いてくれるの?」「うちの子は逃げるば…
リチャードソンジリスは懐く?性格・個体差・懐かせるコツまで解説 小さくて愛らしい姿が人気のリチャードソンジリス。SNSやYouTubeなどでもその可愛らしい仕草が注目を集めていますが、「本当に懐いてくれるの?」「うちの子は逃げるば… - オスとメス、どちらが飼いやすい?
-
一般的には、メスの方が落ち着いていると言われますが、オスでも穏やかな子はたくさんいます。
ライはオスですが、発情期以外はおっとりしていて、攻撃的な面はほとんど見られません。あわせて読みたい リチャードソンジリスはオスとメスどっちが飼いやすい?性格・特徴・飼育のコツを比較解説! リチャードソンジリスをお迎えしようと考えたとき、まず悩むのが「オスとメス、どっちが飼いやすいの?」という点ではないでしょうか。見た目はそっくりなのに、性格や…
リチャードソンジリスはオスとメスどっちが飼いやすい?性格・特徴・飼育のコツを比較解説! リチャードソンジリスをお迎えしようと考えたとき、まず悩むのが「オスとメス、どっちが飼いやすいの?」という点ではないでしょうか。見た目はそっくりなのに、性格や…
病気や飼育に関するよくある悩み
においは強いですか?
オスの方がややにおいが出やすい傾向がありますが、ケージ掃除をこまめに行えばほとんど気になりません。においの強さは体調にも関係するので、急にきつくなったと感じたら体調をチェックしてみてください。

歯が伸びすぎるって本当?
はい、リチャはげっ歯類なので、一生歯が伸び続けます。チモシーやかじり木をしっかり与えないと「オドントーマ」という病気になることもあります。
ケージ内で暴れるときの対処法は?
ストレスや発情期が原因のことが多いです。静かな環境にしたり、布でケージを目隠ししたりして安心できる空間を作ってあげると落ち着きます。
まとめ
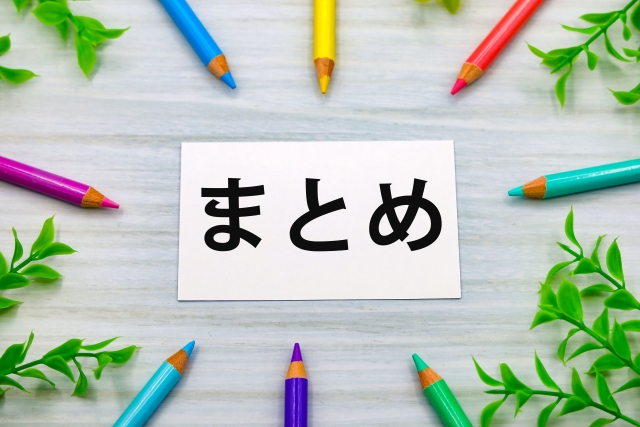
リチャードソンジリスの魅力と飼育の楽しさ
リチャードソンジリスは、見た目の可愛さだけでなく、感情表現が豊かで飼い主との関係性を築ける、まるで“ちいさな相棒”のような存在です。
我が家のライと過ごす日々は、驚きや発見、そして何より癒しの連続です。なつくまでには時間もかかりますし、発情期や健康面での悩みもありましたが、それをひとつずつ乗り越えていくことで絆が深まっていくのを感じています。
この記事を通して、少しでもリチャードソンジリスの本当の魅力や、飼う前に知っておきたいポイントが伝わっていれば嬉しいです。
これからお迎えする方も、すでに一緒に暮らしている方も、自分の子との時間を大切にしながら、楽しいリチャライフを送ってくださいね🐿️
最後までお読みいただき、ありがとうございました!



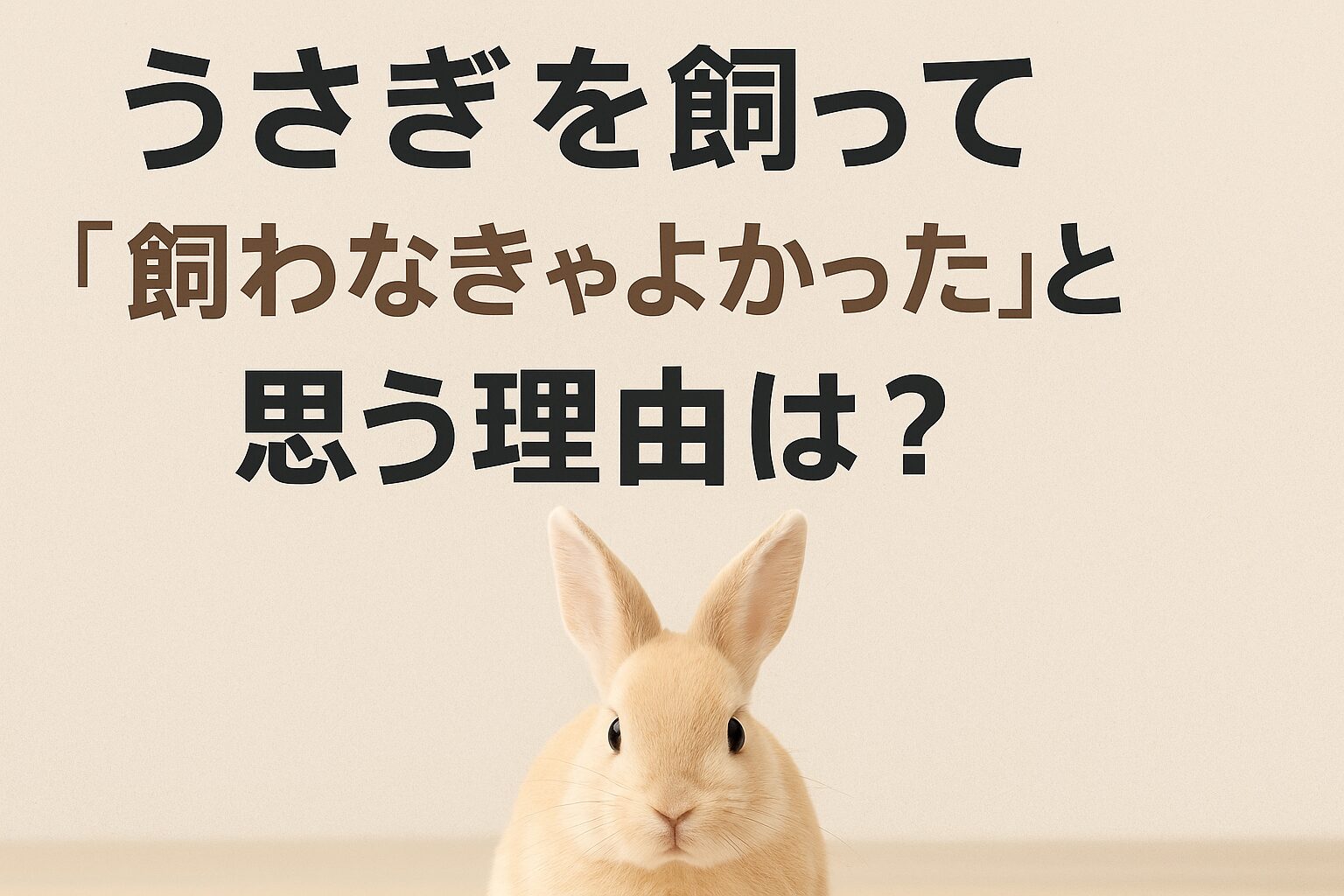



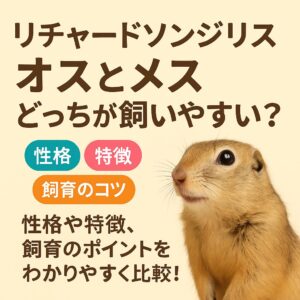
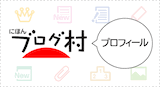









コメント